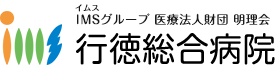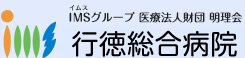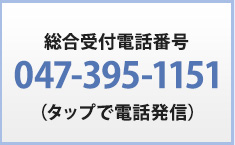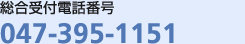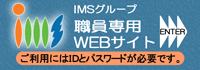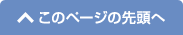小児科
小児科問診票 あらかじめ記入したものをご持参いただくとスムーズに受付がすすみますので便利です。
小児科の特長
中学生までの病気や体調不良、対象年齢だがどの診療科を受診したらいいかわからない場合も小児科で対応いたします。お話をお聞きした上で必要があれば専門診療科に紹介いたします。明らかなケガなどは当院の形成外科、整形外科に最初からお願いしております。発熱を伴う症状では周囲の流行状況を鑑みて、小児発熱外来で対応させていただく場合もあります。お気軽にお問い合わせください。
小児科が対象とする病気や相談内容
感染症(RSウイルス、ヒトメタニューモウイルス、コロナウイルスなどによる風邪、胃腸炎、尿路感染症)、気管支喘息、アトピー性皮膚炎、食物アレルギー、先天性疾患、低身長(成長ホルモン負荷試験)、起立性調節障害、てんかん、注意欠陥多動性障害など、他にも多くの疾患や様々な相談に対応しています。
呼気中の一酸化窒素濃度の測定(気管支喘息の診断)
気管支喘息や咳喘息の診断や治療のために、呼気中の一酸化窒素濃度(FeNO)を測定することができます。気管支喘息の原因は、気管支の慢性的な好酸球性の炎症で呼気中に一酸化窒素が発生します。長引く咳の原因を知りたい、気温の変化で咳き込む、風邪を引くとゼーゼーしやすいなどの悩みに対してFeNOを測定することで気管支喘息かどうかを判断できる検査です。また気管支喘息の治療をしているものの咳が出やすい場合など、治療がうまくいっているかどうかも評価できます。

NIOX VERO (CHEST®︎) パンフレットより
食物アレルギー診断のための食物経口負荷試験
食物アレルギーとは、特定の食品によって引き起こされるアレルギー反応です。食物アレルギーと正しく付き合うには、「本当に食べてはいけない食物」をきちんと知る必要があります。食物アレルギーは血液検査のみで正確に診断することはできません。血液検査が陽性でも必ず症状が出るとは限らず、血液検査が陽性という理由だけで除去をされている方が多いのが現状です。食物経口負荷試験とは、アレルギーが疑われる食品を分割で摂取して、症状の出現を外来や入院で観察する検査です。検査の主な目的は、疑いのある食物が症状を誘発するかどうかを確認(食物アレルギーの診断)、今まで除去していた食物の制限解除や食べられる量の確認です。
スギ花粉症、ダニアレルギー性鼻炎に対する経口舌下免疫療法
スギ花粉症やダニアレルギー性鼻炎をお持ちの方で、内服薬や点鼻薬でも症状が抑えられない方に対して、経口舌下免疫療法を行っています。スギ花粉に対しては「シダキュア」、ダニには「ミティキュア」という薬を舌の下で溶かして服用しアレルギー症状を減らす治療法です。長期間の治療を継続することで、約8割の患者さまにアレルギー症状を抑える効果が期待できアレルギー治療薬を減らすことが期待できます。治療開始時期は、シダキュア(スギ花粉)はスギ花粉が飛散していない6月から12月、ミティキュア(ダニ)はいつでも開始できます。治療が受けられる年齢は5歳以上からです。(成人の方は当院耳鼻咽喉科にご相談下さい)
乳幼児健診や予防接種
乳幼児健診は、定期、任意、入園前健診など全ての健診が対応可能です。
予防接種は、小児の全ての定期予防接種、任意接種に対応しています。また、渡航前ワクチンも事前にご予約・ご相談いただけましたら対応可能です。
これらは予約制で一般外来時間とは別に時間を設けておりますので、感染症の患者さまなどと接触することなく安心してご来院いただけます。
生後3ヵ月までの母乳栄養児にケイツーシロップの毎週服用をおすすめします
以前から新生児は、出生直後、産院の退院時、1か月健診の時にケイツーシロップ(ビタミンK2)を服用しておりました(3回法)。これの目的は、新生児や乳児期早期の体内にはビタミンKが少ないために出血しやすくなり、ビタミンK欠乏性出血症(頭蓋内や消化管に出血)がおきてしまうことを予防するためです。最近、従来の3回法よりも生後3か月まで毎週服用する3か月法の方がより新生児のビタミンK欠乏性出血症を予防できる可能性があることがわかってきました。
2021年11月に日本小児科学会、日本産科婦人科学会、他の関連14団体から、3か月法でケイツーシロップを服用するよう提言が出されました。
当院でもケイツーシロップを処方できますが、予防目的のため自費診療(診察料:税込2,200円、1回分薬剤料:税込110円)となります。一方、哺乳量の半分以上が人工ミルクの場合はケイツーシロップを服用しなくても大丈夫ですが、その際には母子手帳の便カラーカードが4番以上であることを必ずご確認ください。
乳幼児健診・予防接種の時間帯で対応しますので、事前にご予約ください。
HPVワクチン接種行っております
当院では、HPVワクチンのサーバリックス(2価)・ガーダシル(4価)・シルガード(9価)の接種を行っております。
現在HPVワクチン接種は、公費対象となっておりますので、公費番号が分かるものをご持参いただくよう、お願いいたします。対象となる男性の接種も小児科外来で対応しております。
乳幼児健診・予防接種の時間帯で対応しますので、事前にご予約ください。
頭のかたち外来
赤ちゃんの頭の形のゆがみには、頭蓋骨縫合早期癒合症という先天性の病気によるゆがみと、向きぐせによる位置的頭蓋変形症があります。頭蓋骨縫合早期癒合症は頭蓋骨が正常に成長できず、顔面骨も変形し脳が大きくなれないため、神経発達に影響を与えてしまいます。よって手術による治療が必要です。一方、向き癖などで生じる位置的頭蓋変形症(斜頭症、短頭症、長頭症)は、神経発達への影響が無いため病気ではありません。軽度であれば成長と共に自然に改善することが多いですが、ゆがみの程度が強い場合は、体位変換のみでは自然治癒が難しく治りにくいようです。主には整容的な「見た目」の問題となりますが、顔面や耳の左右差への影響が強い場合は嚙み合わせ、視力、眼鏡のかけにくさなどの問題が生じる場合があります。対応としては、こまめな体位変換、タミータイム(うつ伏せ運動)がありますが、程度が強い場合は頭蓋形状矯正ヘルメット療法があります。
頭蓋形状矯正ヘルメット療法の原理は、ヘルメットを装着することで早く成長している部分に成長を待ってもらい、ゆがんでいる部分の成長を促すことで頭の形を均等になるよう改善していく治療法です。ヘルメットでの矯正治療をご希望する場合、当院では株式会社Berryのべビーバンド®を採用しております。詳細は下記のリンクをご覧ください。料金は自費診療(ヘルメット代や外来診療費用を含み、税込み346,500円)になります。ヘルメット治療の開始時期は生後3ヶ月からで、治療期間は約2~6ヶ月間です。生後3~4ヶ月頃の開始が最も効果が期待できるようです。対応している外来日は、月曜日、火曜日と木曜日の乳児健診の時間帯です。事前に予約のご連絡をお願いします。
外来担当医表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
|
|
|
|
|
|
| 午後 |
|
|
|
|
|
担当医表(PDF版のダウンロード)
休診・代診情報
医師紹介
小児科
森本 由希(もりもと ゆき)
| 専門分野 | 小児科 |
|---|---|
| 略歴 | 平成14年3月 琉球大学卒業 平成14年4月 日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 平成16年4月 日本赤十字社 名古屋第二赤十字病院 麻酔科 平成20年4月 学校法人藤田学園 藤田保健衛生大学病院 小児科 平成21年4月 医療法人豊田会 刈谷豊田総合病院 小児科 |
| 資格 |
|
| 所属学会 |
|

森本 由希 医師が講師を務めた健康教室
- おやこカフェ「感染症のお話」
- おやこカフェ ~病院との付き合い方について小児科の先生と話そう~
- あなたも10歳若返る!?~美しい姿勢と深い呼吸で毎日を健康的に~
小児科
後藤 昌英(ごとう まさひで)
| 専門分野 | 小児科 |
|---|---|
| 略歴 | 平成17年 自治医科大学 卒業 平成17年 茨城県立中央病院 平成19年 茨城県立こども病院 平成22年 国立精神・神経医療研究センター 脳神経小児科 平成24年 常陸大宮済生会病院 小児科 平成26年 北茨城市民病院 小児科 平成29年 自治医科大学大学院医学研究科博士課程 卒業 平成29年 自治医科大学付属病院 小児科講師 令和01年 University of Illinois at Chicago 令和03年 行徳総合病院 小児科・遺伝カウンセリング外来 |
| 資格 |
|
| 所属学会 |
|