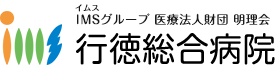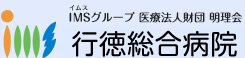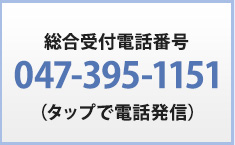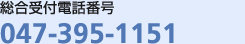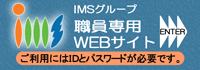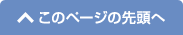乳腺外科
外来担当医表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 |
|
|
|
|
|
|
| 午後 |
|
|
|
|
|
担当医表(PDF版のダウンロード)
休診・代診情報
ただいまデータ読み込み中です。